(1)歩行不自由なお客様とは |
歩行補助具(杖、松葉杖、シルバーカー等)や装具(義肢等)を利用のお客様。または高齢による運動機能(骨・筋力)低下や、それに伴う疾患で関節に金属が入っているお客様です。義肢や金属が入っている方は、外見からの判断は難しいです。脳疾患の後遺症で片麻痺になったり、その他疾患の影響による運機能障がい、事故により片足を切断するなど、原因によって状態は異なります。また、補助具の利用を始めて経験が浅いのか、十分に慣れているのかといった経験の長さによって、歩行のスピード、歩幅の大小や歩行可能な距離も異なります。
疾患がなくても、杖歩行の高齢者の歩行は健常の高齢者と異なり、一般的に速度が遅く、歩幅も狭いです。 |
|
歩行の不自由なお客様への応対ポイントと留意点
|
- 歩行補助具や装具を利用のお客様が困るのは雨や雪の日の歩行です。足下が滑りやすく、傘を持っている場合には、とっさの時の行動が素早くできません。また、強風の時もバランスを失いやすいものです。松葉杖を利用の方は傘をさすことも困難です。予想外の悪天候になったときのことも検討してご対応しましょう。介助者も含め雨合羽のご用意は必要です。
- 歩行のスピードは遅くなりがちです。観光地めぐりや美術館・展示館などの施設の見学時間、移動の時間、歩く距離については十分に話し合い、ゆとりを持ったプランを計画、またはお勧めするようにしましょう。
- 参加者の多い団体ツアーの場合、歩行速度を他のお客様に合わす事が難しいことが多いです。お客様おひとりごとの歩行速度に合わす事ができないことをご説明しましょう。
また、海外ではバス内で待つことができない場合もありますので、ご案内に注意しましょう。
旅行先によっては、団体ツアーより個人プランのツアーに専用車などを組み込むことにより、お客様のペースで行動でき有意義な旅になります。また、障がいの度合いによっては、バリアフリー専門ツアーに参加することにより、訪問国や観光の範囲が広がる場合もあります。
- 歩く距離、移動の時間や観光場所によっては、空港や現地で車いすを借りたり、持参をされた方が楽な場合もあります。但し、車いすで走行できない環境がある場合は、事前にご説明をしましょう。特に車いすが利用できない階段や段差の場所では、介助者がその都度、持ち上げることになることもご案内をしておきましょう。特にヨーロッパの石畳や坂、階段の多い旅程では車いすを押すことに慣れていない介助者にも負担となります。車いすを利用したほうがよい旅程かどうか、十分に確認をしましょう。
- 歩行車(車輪の付いている歩行器)は体の両脇に手を下ろした位置にハンドルがくる為、体をまっすぐに起こした状態でハンドルが持てます。一方、シルバーカーは手押し車である為、手は常に体より前になり、前傾姿勢となります。よって斜面ではスピードが出やすい為、注意が必要です。
歩行車もシルバーカーも座面のついた軽量なタイプがある為、比較的軽度な高齢者の場合、持参されると美術館や展示館では便利な場合もあります。
- 大きな荷物は持てないお客様が大半です。ご自身のお荷物はできるだけ歩行に負担にならないように小さくまとめる事をお勧めしましょう。また、お買い物の際は、別送の案内などを心がけましょう。
|
|
(2)車いす利用のお客様とは
|
車いすを利用されるお客様の事情や障がいの程度は様々です。脳性マヒ、筋ジストロフィー、先天性骨形成不全などの先天性の場合、交通事故やケガ(脊髄(せきずい)損傷など)、病気(脳疾患の後遺症、リウマチ、難病など)による後天性の場合によって異なります。また、手の障がい、上半身障がい(上肢麻痺等)や言語障がいを伴ったりする場合もあります。進行性の難病の場合、少しずつ障がいの状態は変化していきます。
また、車いすには「手動車いす」やバッテリーを利用する「電動車いす」、普通の手動車いすにバッテリーを装着して電動使用が可能な「手動・電動兼用使用車いす(軽量型電動車いす)」などがあり、それぞれに注意する点、お伺いするポイントが異なります。 |
|
車いす利用のお客様への応対ポイントと留意点
|
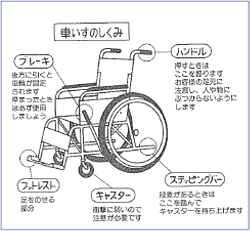 お話しする際は、車いすに座っている方を見下ろすことのないように、お客様と目の高さを合わせるようにしましょう。 お話しする際は、車いすに座っている方を見下ろすことのないように、お客様と目の高さを合わせるようにしましょう。- まず、障がいのあるお客様ご本人とお話しするようにしましょう。その際は、車いすに乗っているからと口調を変えることなく、一般のお客様と同じような対応をしましょう。
- 車いす利用者は、一般のお客様より視線が低く、視界の縦幅が狭いこともあり、表示板が見えにくい場合があることを認識しましょう。お客様の視点から見えているかどうか、確認をしましょう。
- 空港や駅などの施設でエレベーター使用のため、団体から離れることもあります。必ず待ち合わせ場所の確認をしましょう。
- 同行の介助者が車いすを押すことを原則としますが、イレギュラー時の対応に備え、車いすの各部の名称、基本的な機能や操作の方法は知っておくことが望ましいでしょう。
- 車いすを押すときには、車いすに乗っている方の足がフットレストの上にあることを確認しましょう。人や物にぶつからないように気をつけましょう。また、止まっているときには、必ずブレーキをかけ、押すときには、忘れずにブレーキの解除をしましょう。
- バスの乗降では車いすの収納方法を確認し、搭載時の破損に注意しましょう。また、手荷物やクッションなどの忘れ物をチェックしましょう。
- ホテルやレストランなどで食事の際、バイキング料理の皿がもてない、手が不自由で肉が切れないなど、困ることも多いので常に全体に視線を配りましょう。また、お客様の状態によっては、お食事への配慮(細かく切ったキザミ食など)が必要かどうかを事前にお伺いし、ホテル、レストランへ対応可否の確認を事前に行っておくことも大切です。
- ホテルの部屋について(室内の段差の有無、ベッドの高さ、風呂やトイレの広さや設備など)早めにお客様へお知らせすることも大切なポイントです。
- 利用施設のドアや通路の幅をチェックするために、車いすのサイズ(幅・奥行・高さ)を確認します。
<電動車いす>
-
電動車いすのバッテリーによっては、液漏れの恐れ等があるため、航空機へ受託および持ち込む際、また船内に持ち込む際に制限があります。
車いすのバッテリーの種類*や重量を必ず確認します。(*後述参照
- 通常、車いす自体の重量が重く、折りたたみができません。しかし、軽量型電動車いすについては、折りたたみができるタイプもあります。
- バッテリーの充電が必要になるため、充電器及び変圧器(海外:電圧が異なる場合)が必要になります。
|
|
◆リフト付きバス・リフト付きワゴンの手配で配慮する点 |
- 車いす利用者にとっては、リフト付きバスやワゴン車は、次の点で非常に便利です。
- 乗降時の介助者の労力が大幅に軽減されます
- 乗降時の障がいのあるお客様の危険が少なくなります。
- お客様を抱きかかえての介助は一般的に好まれません。
- 車内で車いすに座ったままの場合、長距離(長時間)の乗車では疲れるため、不向きなこともあります。1時間以上の乗車では、座席に座っていただいた方が、車いすを利用するお客様に楽な場合が多いようです。
一方、安全面から、車内では車いすから座席に移動をしないと走行できない場合もありますので、車両会社に確認をしましょう。
- リフト付きバスを利用しても、乗り降りの時間が短縮されるわけではありません。
利用者の多い場合、リフトの操作で乗降に余計に時間がかかることもあります。
- 車体のサイドなどから車いすを持ち上げる「リフトアップタイプ」のほかに、車体後部ドアからスライド式スロープを使って乗車する「スロープタイプ」など福祉車両にも種類があります。お客様がどういったタイプを希望されているのかヒアリングも必要です。
また、バンタイプで傾斜板を利用して乗降可能な車両もあります。
- 車種によって車いす固定座席数が異なるので、事前の確認が必要です。
また、搭載するお客様の荷物の大きさ、数も一緒に搭載できるかどうかの確認が必要です。
|
|
 |
◆宿泊施設において配慮する点
|
項 目 |
チェック内容 |
駐車場
出入口
|
- 出入口から近いかどうか
- 段差はないか、スロープはあるか(傾斜角度は何度か:1/12以下)
|
エレベーター |
- 鏡はあるか(後ろ向きで降りる際のバックミラーの役割)
- ドアの開口部の幅はひろいか(最低80cm以上)
- 内部の広さはどの程度か
|
すべてのドア |
|
客室 |
- ハンディキャップルームを希望する場合、希望のお部屋タイプに用意があるかどうか
- 車いすで回転スペースがあるか(直径路150㎝以上)
- 浴室に手すりはついているか。
- シャワーチェアはあるか、又は貸し出しがあるか。
- ハンドシャワーかどうか
- 洗面台の下は車いすの場合、足元が入るようになっているか
- 浴室のドアは内開きか、外開きか
- ベッドの高さ
|
トイレ |
|
|
◆航空機を利用する際の留意点
|
場面 |
チェック内容 |
チェックイン
カウンター |
- お客様の特別な手配に関する予約を航空会社に早めに確認する。 (機内用車いす、特別食、座席のご要望、搭乗口までの誘導など)
- お客様ご自身の車いすの預け場所を確認する。(一般的に、お客様はできる限りご自身の車いすを利用したい希望を持っているが、空港・航空会社の運用上、チェックインカウンターで航空会社の用意する車いすに乗り換えることが基本となっている)
- 車いすを数に含め、受託荷物の個数を確認する。(車いすにクレームタッグや「取扱い注意(FRAGIL)」タッグをつけてあるかを確認する。電動車いすのバッテリーで「危険物扱い」になる場合は特に注意して確認をする)
|
CIQ(出国審査・税関・検疫)手続き※ |
- 特別な留意事項はない。同行添乗員等は、事前に車いす用トイレの場所、搭乗口への誘導の際の階段やエレベーターの有無を確認しておくと良い。
|
搭乗・降機 |
- 通常、一般に搭乗者より先に優先搭乗となることが多い。介助者も一緒にご搭乗開始時刻より早い時間にご搭乗口付近にお越しになることをご案内する。
- ご自身の車いすを搭乗口での受託となる場合、行き先を確認する。
- 降機の順番については、通常、一般の搭乗者が降機した後になる。
|
機内 |
- 同行添乗員は、客室乗務員と特別な手配内容について確認をしておく。(機内用車いす、特別食、その他追加手配など)
- 機内に車いす用トイレがある場合、その場所と利用方法を確認しておく。
- トランジットで途中待機となる場合には機内に留まるのか、待合室に行くのかをお客様に早めにお知らせする。
|
到着空港 |
- CIQの手続きの際、エレベーター利用などの建物の構造上で車いすを利用する方と利用しない方が別れることも多い。※
- お客様の中には医薬品を相当量持参している場合もある。税関での検査で薬品の内容について聞かれた場合に備え、英文の薬剤証明書等の持参をあらかじめ勧めておくとよい。※
- 受託した車いすを到着ロビー手荷物引取所で受け取る。
|
その他 |
- 空港内の車いすトイレの場所を早めに確認する。
- 現地旅行会社の係員とは特別な手配内容(宿泊施設へ別途依頼しているサービスなど)について早めに確認しておく。
|
※国際線利用時のみ。 |
◆鉄道を利用する際の留意点
|
場面 |
チェック内容 |
出発前 |
- お客様の特別な手配に関して、鉄道会社に早めに依頼をする。
(座席までの誘導など)
- 車いす用の指定席が必要な場合は、可能な限り1か月前の発売日(JRの場合)に指定予約をする。
- エレベーターやスロープのバリアフリールートを確認しておく。
|
乗車・降車 |
- 幅の広い改札口に誘導する。
- 一般の通路と別の通路を通り、改札口から列車まで移動することもあるので注意する。
|
車内 |
|
その他 |
- 駅構内・車内の車いす用トイレの場所を早めに確認する。
|
|
◆バスを利用する際の留意点
|
場面 |
チェック内容 |
出発前 |
- あらかじめバスの種類を確認しておく。
- 車内に車いすを固定するスペースがあればその場所と台数を確認する。
- 固定スペースがある場合、シートベルトも付いているか確認する。
(付いていない場合は座席に移乗していただく)
- 車いすのまま固定するか、座席に移乗するのかを事前に確認する。
- 道路脇で乗車する場合は周囲の安全が確保されているかどうかが重要となる。
- リフト付きバスの場合、リフトを降ろすスペースがあるか確認をする。
- 床下のトランクルームに車いすが収納可能か確認をする。
|
乗車・降車 |
- リフトやスロープ付き車両の操作は、乗務員に任せる。
- 介助者が抱え上げ、乗車される時は、落下事故などに気をつける。
できるだけ乗降口近くの座席に座っていただき、シートベルトで固定するなど、身体が動かないように注意する。
|
車内 |
- 車いすのままの長時間の乗車は疲れるため、座席に座っていただいた方が、車いすを利用するお客様も介護者も楽な場合もある。
|
|
◆船舶を利用する際の留意点
|
場面 |
チェック内容 |
出発前 |
- 乗下船の方法を船会社に確認する。
(乗下船時にのみ車いすの貸出を行っている場合もある)
- お客様の特別な手配に関して、船会社に早めに依頼をする。
(座席や客室のご要望など)
- 個室客室の場合、バリアフリー対応の客室があるかどうかを確認する。
|
乗車・降車 |
- 通常、一般の搭乗者より先に優先乗船となることが多い。介助者も一緒に乗船開始時刻より早い時間に出発ターミナル付近にお越しになることをご案内する。
- 最終寄港地での下船は通常の場合、優先下船となる。
- お客様の中には医薬品を相当量持参している場合もある。海外の場合は、税関検査で薬品の内容について聞かれた場合に備え、英文の薬剤証明書等の持参をあらかじめ勧めておくとよい。
- 乗船後、館内のバリアフリーを確認する。
|
車内 |
- 船内の車いす用トイレの場所を早めに確認する。なお、大型客船以外には車いす用のトイレがない場合が多いので、事前に確認を行い、出発前に必ずご案内をする。
- 寄港地によってはテンダーボートでの上陸となり、車いす利用のお客様は上陸できない場合もある。
|
|
◆観光施設等を利用する際の留意点
|
場面 |
チェック内容 |
|
- 階段、斜面、出入口の段差などないか、事前に確認をしておく。
- 砂浜、芝生など、車いすが利用しにくい場所や杖を利用しての歩行に、適していない場合は、無理のない範囲までの観光にしていただく。
- 石畳などは車いすでは介助者への負担も大きくなり、杖歩行では足への衝撃も強くなる為、速度は落ちることを認識し旅程管理を行う。
- 足元が悪い場所については、転倒に十分に注意いただくようご案内する
- 車いす対応トイレの有無とその位置をご案内し、早めにご利用いただくようにご案内をする。レストランではトイレが階段を利用しない位置にあるかを確認することも大事です。
- 全ての動作に一般のお客様より時間を要する為、食事の際も先に提供するような依頼も大切です。
- 集合時間に間に合うように、早め早めの行動を促す。
|
|
(3)車いす利用のお客様に起こりうる事故・トラブル
|
①車いすの転倒など |
- 車いすの前方の小さい車輪(キャスター)が、空港の動く歩道(moving sidewalk)やエスカレーターなどで降りる最後のステップに詰まって動かなくなり、事故に繋がることがある。
*そのような所では、前輪を少し持ち上げる必要がある。
- 車いす利用者の体重が介助者の体重よりずっと重い場合(50kg の母親と60kg の息子)には、下りの坂道では前方に倒れてしまうケースがある。
*下りの坂道では傾斜が急な場合は、必ずうしろ向きで下りる。
*ベルトをしっかり締める。
- 前輪が道路の鉄格子状の排水溝にはまって、動かなくなった瞬間、前方に転倒し、顔を道路にぶつけることがある。
*添乗員は、車いすの前輪が落ち込みそうな箇所がないか注意する。
- 普段、車いすを使用しており多少歩行ができる方とか、半身不随で杖を使っている方などが、小さな段差に気づかず転ぶことがある。
*介助者に支えてもらう。
*半身不随の場合、利かない方の手を持って支える。
- 普段、車いすに乗り慣れていない場合、降りる時に前方のフットレストに、つまずいて転倒することがある。
*必ず、フットレストをはねあげてから、降りてもらう。
- 普段、車いす介助に慣れていない場合、ブレーキ解除をせずに強引に押し、車いすごと転倒することがある。
*必ず、ブレーキの解除と斜面でブレーキをかけることを忘れないようにする。
- 車いす利用者で、多少の歩行ができる方が、ホテルの浴槽に滑り止めゴムマットがなかった為、浴槽内で転倒してケガをしたケースがある。
*車いす利用者の入浴は、必ず介助者と一緒に行っていただく。
*とくに滑りやすい状態の場合は、慎重に歩行していただく。
|
②ホテルのハンディキャップルームの使い方
欧米のハンディキャップルームは、自分で設備の操作ができる人を想定したものが多く、浴室はバスタブでなく、シャワーだけのところが多い。排水溝は備わっているが、シャワーカーテンを利用しても慣れない使用から、洗面台やトイレ周辺が水浸しになる場合がある。バスタオルを余計に借りる等、利用者の工夫が必要である。 |
③観光施設のリフト(階段昇降機)が故障していて、車いす利用の方が入場できない場合
- 施設の人に相談し、介助にて対応可能な状況場所であれば、施設の人に手伝っていただく。
- 介助でも困難な状況場所においては、業務用のエレベーターの有無、使用の可否を確認する。
|
④車いすなどの故障に際し
- 旅行前に車いすの各部署(ネジやタイヤなど)に不具合がないか、事前に点検をしておくことをお客様にお勧めする。
- イレギュラー時に備え、現地の介護機器会社なども確認しておくとよい。
|
⑤その他
徒歩観光の多いツアーに、杖利用で歩行されるお客様が参加されたが、障がいの状況を十分確認しなかったため、全体の行程が遅れる場合がある。
- 旅行申し込み受付時において、「車いす利用ではなく、歩行ができれば旅行は大丈夫」と解釈して予約を受けた事例。車いす利用ではなくても、ツアーによりご参加に適していない旅程がある。障がいの詳細とコース内容を、十分確認する必要がある。
|
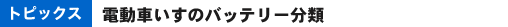
|
| 分類 |
特徴 |
ウェット
バッテリー |
ウェット
バッテリー
|
「硫酸鉛バッテリー」といい、希硫酸が入っている。充電時に発生する水素と酸素を逃がすため、バッテリー注入キャップに小さな穴があいており、横倒しで割れると大量のバッテリー液が漏れる。 |
ドライ
バッテリー |
ニッケル水素
バッテリー |
従来の携帯電話やビデオのバッテリーとして使用されており、希硫酸を全く使用していない。取扱いは比較的、簡単で安全。 |
リチウムイオン |
携帯電話やノートパソコンのバッテリーとして使用されている。小型で軽量であるが、航空機の持ち込みに容量制限がある。 |
シール
バッテリー |
極板と極板の間にティッシュペーパーのようなものが入っており、そこに希硫酸をしみこませている。横倒しにしても漏れはないが、落として割れると水滴程度のもれが生じる。 |
|
参考:電動車椅子で航空機を御利用される場合のルールについて(国土交通省HPより)
http://www.mlit.go.jp/common/001005802.pdf |

車いす利用のお客様を含む家族3名様がヨーロッパ周遊コースにお申込みされました。行程のなかには、階段を使って、建物でいえば7~8階程度の高さまで登る必要のある観光施設が数か所あり、あいにく、車いすでは登れないため、カフェなどでお待ちいただく必要があるとご案内しました。すると、お客様から「今回の観光地はほとんど見たことがあり、それを孫に見せたいというのが希望です。その間、自分は無理せず途中で待っているつもり」とお返事がかえってきました。
このように、たとえ歩行の不自由な方がヨーロッパ周遊コースへ参加を希望されるケースであっても、表面的な理由だけでお断りすることなく、お客様の旅行の目的を伺うことが必要ですね。
|
(4) Q&A
|
Q. |
10月末、イタリアへの団体ツアーに参加のお客様。脳卒中後の後遺症で、歩行は可能だが車いすを利用したい。 |
A. |
日本からご持参いただくことをお勧めする。空港やホテルでは貸出用車いすを用意している箇所は多い。その他レンタル業者はあるが、次のような問題点がある。
(1)ホテル内だけでの使用制限がある場合がある (2)滞在都市が移動する場合、現地でのレンタル業者とトラブルが起きた場合、ツアー行程に影響する (3) 車いすが体格と合わないケースもある。 (4)レンタル料金が日本からレンタルするより高い場合がある
|
Q. |
シルバーカーを持参してモンサンミッシェルに行かれたいとの旅行相談を受けたが、観光は可能でしょうか? |
A. |
モンサンミッシェルは、駐車場から入り口までのおみやげ物店が並ぶ参道は坂道であり、また修道院内も350段近い階段がある為、持参されても歩行補助具としての役割をしない。持参をしても荷物として持ち運ぶだけになるので、バス内に置いて行くことが望ましい。あらかじめ添乗員に相談して、歩行可能なところまで観光され、参道のカフェで休憩をして待つようにするのが望ましい。 |
Q. |
お嬢様が、脳疾患の後遺症で体幹機能全廃のお母さまを沖縄に連れて行きたいが、ホテルでの滞在時、二人では心配。日常生活での介護ヘルパーさんの旅行代金を払う余裕はない。どうしたらいいでしょうか? |
A. |
滞在先のヘルパーさんを手配することにより、飛行機代の負担がなく宿泊費のみの介護ヘルパーさんの費用負担で済む。沖縄到着後から滞在期間中、介護していただけるヘルパーさんを手配することをご提案する。
介護の希望内容や相性もある為、お客様ご自身でお手配いただくことが望ましい。 |
|